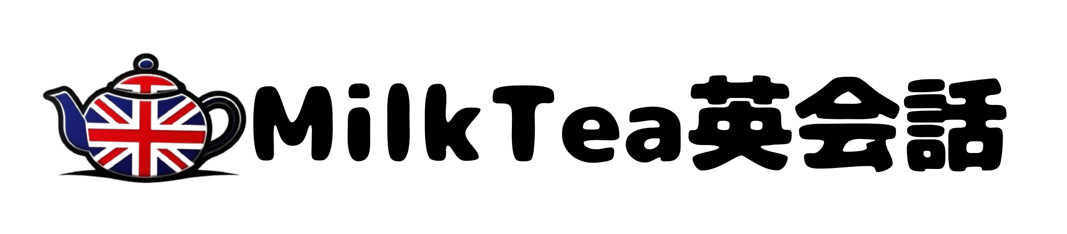前置詞ofの奥深き世界を徹底解説!前置詞の世界を分析しようシリーズ

英語を学ぶ上で避けて通れないのが、前置詞「of」の使い方です。たった二文字のこの単語には、実に多様な意味と用法が込められており、文の意味を左右する重要な要素です。本記事では、「of」の13の使い方について解説します。
- 使い方1:誰かに属する/誰かと関係があることを示す「of」: 名詞 of [人物]
- 使い方2:物や事柄に属する・一部をなす「of」(belonging to something; being part of something; relating to something): [部分] of [全体]
- 使い方3:出身・居住地を表す「of」: [人] of [出身・居住地]
- 使い方4:人物や物を描写・示す「of」
- 使い方5:構成要素や中身を示す「of」(used to say what somebody/something is, consists of or contains)
- 使い方6:時間・年齢・数量などの表現に使われる「of」
- 使い方7:一部を示すときの「of」
- 使い方8:位置や時間を示す「of」
- 使い方9:動詞由来の名詞とセットで使う「of」(The noun after ‘of’ can be either the object or the subject of the action.)
- 使い方10:動詞の後に置かれ、動作に関わるもの・人を示す「of」
- 使い方11:形容詞の後に使われる「of」
- 使い方12:「人の行動に対する意見」を表すof
- 使い方13:「of」が名詞を強調する用法
使い方1:誰かに属する/誰かと関係があることを示す「of」: 名詞 of [人物]
前置詞「of」は、「誰かに属する」「誰かに関係する」といった意味で頻繁に使われます。これは最も基本的な使い方の一つで、「〜の友達」「〜の母の愛」「〜の役割」といった表現に見られます。日本語でいう「〜の」に対応し、「所有」や「関係性」を示す役割を果たします。
この用法では、必ずしも「物理的な所有」を示すのではなく、「人間関係」や「抽象的な関係性」も含まれます。英語では「Tommyの古い自転車」や「母の愛」などを、ofを用いて表現します。
例文と解説
a friend of mine
私の友人の一人
→「mine(私のもの)」とセットで使われ、所有関係を強調する表現です。友達全体の中の「一人」であることを示します。
the love of a mother for her child
母親の子供への愛
→この文では、「母親の愛」という所有的な意味があり、「誰の愛か」を明確にしています。
the role of the teacher
その教師の役割
→「誰の役割か」を示すために、「of the teacher」を使っています。抽象的な「役割」という概念に、「教師」という主体が付与されています。
Can’t you throw out that old bike of Tommy’s?
トミーのあの古い自転車を捨ててくれない?
→「of Tommy’s」は、やや口語的な形で、「Tommyが所有しているもの」の意味を強調しています。
the paintings of Monet
モネの絵画
→「of Monet」は、所有と同時に「作者としての関係」を表しており、「誰によって描かれたか」という視点も含みます。
補足:この「of」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この所有や関係性を示す「of」は、以下のような単語とセットで使われることが多いです。
- a friend of 〜(〜の友人)
- the work of 〜(〜の作品)
- the name of 〜(〜の名前)
- the idea of 〜(〜の考え)
- the opinion of 〜(〜の意見)
このように、人物を主語または目的語とする抽象名詞と「of」を結びつけることで、「誰に関するものか」「誰に属するものか」という情報を伝えることができます。
まとめ
前置詞「of」の使い方1では、主に「所有」や「関係性」を示す役割がありました。この用法は日常会話でも文章でも頻繁に登場する基本表現でありながら、使い方を間違えると意味がぼやけてしまいます。特に抽象名詞や人名と組み合わせることで、「〜の誰々」「〜の何か」という形で自然な英語表現が完成します。
使い方2:物や事柄に属する・一部をなす「of」(belonging to something; being part of something; relating to something): [部分] of [全体]
この使い方では、前置詞「of」は「〜の一部」「〜の構成要素」「〜に属するもの」などの意味を持ちます。あるものが何かの一部であること、あるいは何かに関連していることを示すときに使われます。
たとえば、「the lid of the box(箱のふた)」や「a member of the team(チームの一員)」といった表現において、前置詞「of」は「どの箱? → ふたが属している箱」や「どのチーム? → メンバーが属するチーム」といった所有や関係性を示しています。
この用法は、物理的なモノの構成だけでなく、組織や集団のメンバー、抽象的な概念(例:議論の結果など)に対しても使われます。
例文と解説
the lid of the box
箱のふた
→「ふた」が「箱」に属している、つまり構成要素であることを示しています。
the director of the company
その会社の取締役
→「会社」という組織の中の一部である「取締役」であることを示しています。
a member of the team
チームの一員
→「team」という集団の一部である「member」が、ofによって関係づけられています。
the result of the debate
議論の結果
→「debate」という出来事から生まれた「result」であり、原因・起点を表す意味合いも含んでいます。
このように、「of」を使うことで、何かが別の何かの構成要素であること、所属していること、由来していることなどを明確に伝えることができます。
補足:この「of」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この構成・所属を示す「of」は、以下のような言葉とセットでよく用いられます。
- part of 〜(〜の一部)
- member of 〜(〜の一員)
- result of 〜(〜の結果)
- section of 〜(〜のセクション/部分)
- head of 〜(〜の長/トップ)
構成要素・メンバー・結果・部署など、「全体」と「部分」の関係を表す名詞との相性が良く、英語表現に自然な一貫性を持たせてくれます。
まとめ
「of」の使い方2では、「物や人がある全体の中の一部であること」を表すために使われることを学びました。この用法は、組織構造や物理的な構成、抽象的な関係性まで幅広くカバーしています。
文法的に正確に、かつ自然に意味を伝えるためには、この「全体と部分」の関係を理解することが大切です。
使い方3:出身・居住地を表す「of」: [人] of [出身・居住地]
この用法では、「of」はある人がどこから来たのか、どんな背景を持っているのか、またはどこに住んでいるのかを示すために使われます。つまり、「〜出身の」「〜に住んでいる」といった意味を表すときに「of」が活躍します。
たとえば、「a woman of Italian descent(イタリア系の女性)」のように、血統や祖先の国を示したり、「the people of Wales(ウェールズの人々)」のように、居住地を示す表現に使われます。この「of」は、出自や所属するコミュニティ、文化的背景などを明示するのに非常に便利です。
例文と解説
a woman of Italian descent
イタリア系の女性
→「descent(血統・祖先)」を通して、「イタリアに起源を持つ女性」という出自を表しています。
the people of Wales
ウェールズの人々
→「Wales(ウェールズ)」に住んでいる、あるいはそこに由来する人々を表しています。
この用法では、地名や国名、文化、祖先などが「of」の後に来ることが多く、出身や所属を明示するのに役立ちます。また、文学的・正式な文体でよく使われ、文章に品格を与える表現にもなります。
補足:この「of」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この「出自・居住」を表す「of」は、以下のような表現とよく組み合わされます。
- man/woman/person of [nationality/descent]
例:man of French origin(フランス出身の男性) - people of [place]
例:people of Tokyo(東京の人々) - citizen of [country/city]
例:citizen of the United States(アメリカ合衆国の市民) - residents of [area]
例:residents of this neighborhood(この近所の住人たち)
これらの表現は、出身地や住まい、文化的なバックグラウンドを自然に伝えることができます。
まとめ
「of」の使い方3では、人の出自・出身・居住地を表すために使われるパターンを学びました。この用法は、単なる所有を超えて、文化的背景やアイデンティティを含意する豊かな表現を可能にします。
使い方4:人物や物を描写・示す「of」
この用法では、「of」は人や物に関する情報を追加し、それが何を表しているか、または誰・何に関するものかを示します。特に、「写真・物語・地図・イメージ」などの名詞の後に続く「of」は、その内容や対象を特定・描写する役割を果たします。
たとえば「a photo of my dog(私の犬の写真)」という表現では、「photo」が何の写真なのかを「of」によって明らかにします。この構文は非常に広く使われており、日常英会話でもよく登場します。
例文と解説
a story of passion
情熱の物語
→ この表現では、「story」が「情熱」について語っていることを示します。
a photo of my dog
私の犬の写真
→ 「of」は、「photo」が誰・何を写しているかを明らかにします。この場合は「my dog(私の犬)」です。
a map of India
インドの地図
→ 「map」がどの地域を描いたものなのか、「of」が示しています。
この使い方の「of」は、特定の「主題(テーマ)」や「内容」を明示するために使われ、視覚的・物語的な情報に関係する名詞と組み合わされることが多いです。
補足:この「of」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この使い方の「of」は、以下のような名詞と頻繁にセットになります。
- a picture/photo/image of ~
例:a picture of Mount Fuji(富士山の写真) - a story/tale of ~
例:a tale of bravery(勇気の物語) - a map/diagram/plan of ~
例:a diagram of the heart(心臓の図) - a record/account of ~
例:an account of the event(その出来事の記録)
これらの表現は、「何についてのものなのか?」という問いに答える非常に基本的かつ重要な構文です。英語学習者にとっても必須のパターンといえるでしょう。
まとめ
「of」の使い方4では、名詞の内容・対象を特定・描写するための構文を学びました。話す内容に具体性を加える非常に便利な表現であり、会話・ライティング問わず多用される用法です。
使い方5:構成要素や中身を示す「of」(used to say what somebody/something is, consists of or contains)
この用法では、「of」は何かが何から構成されているのか、何を含んでいるのか、どのような性質を持っているのかを示すために使われます。カテゴリー分けのofという感じ。例えば、The issueで「何のisuue?」→「housing」のisuue →the issue of housing
また、「a glass of milk(牛乳一杯)」という表現では、「glass(コップ)」の中身が「milk(牛乳)」であることを明確にしています。このように、「of」は量や中身、構成する要素を示すときに不可欠です。
例文と解説
the city of Dublin
ダブリンという都市
→ 「Dublin」は「city(都市)」の具体的な内容を示しています。つまり、「どの都市か?」を「of」で明らかにしています。
the issue of housing
住宅問題
→ 「issue(問題)」が「housing(住宅)」に関することであることを、「of」によって示しています。
a crowd of people
人々の群れ
→ 群れ(crowd)が何で構成されているのか、「people(人々)」であることを示します。
a glass of milk
牛乳一杯
→ コップの中身が「milk(牛乳)」であることを表します。
この使い方は、抽象的な概念や具体的な物体の構成内容を明確に伝える役割があります。英語では非常によく使われる自然な表現の一つです。
補足:この「of」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この構成・中身を表す「of」は、以下のような名詞と頻出で結びつきます。
- a glass/bottle/cup of ~
例:a bottle of water(水のボトル) - a group/crowd/team of ~
例:a team of experts(専門家のチーム) - a piece/slice/drop of ~
例:a piece of cake(ケーキ一切れ) - the topic/issue/question of ~
例:the question of identity(アイデンティティの問題)
これらの表現は、話の中で対象の詳細や構成を説明したいときに非常に役立ちます。日本語の「〜の」と似ていますが、より具体的な関係性に注目して使うのがポイントです。
まとめ
使い方5では、「of」を使って物事の構成や中身、内容を示す方法を学びました。これは日常会話からビジネスシーンまで広く使われる、非常に汎用性の高い用法です。英語表現を豊かにするために、ぜひマスターしておきたいですね。
使い方6:時間・年齢・数量などの表現に使われる「of」
この用法の「of」は、数量、時間、年齢、割合などの具体的なデータを示すときに使われます。数値や時間に関する情報を名詞として表現する際、「of」はそれらの関係性を明確にします。
たとえば、「a girl of 12(12歳の少女)」という表現では、少女の年齢が「12」であることを意味しています。また、「2 kilos of potatoes(ジャガイモ2キロ)」では、量(2キロ)と中身(ジャガイモ)を結びつけています。
このように、「of」は数値を説明の一部として取り込むために非常に便利で自然な英語表現の一つです。
例文と解説
2 kilos of potatoes
ジャガイモ2キロ
→ 「2 kilos(2キロ)」という量が、「potatoes(ジャガイモ)」にかかっています。量と中身を示す典型的な表現です。
an increase of 2 per cent
2パーセントの増加
→ 増加の度合いが「2パーセント」であることを表す「of」の使い方です。経済や統計などの文章でよく見られます。
a girl of 12
12歳の女の子
→ 「of」は「年齢が12歳である」という意味を添えて、「girl(女の子)」を説明しています。
the fourth of July
7月4日
→ アメリカ独立記念日などでも使われる日付の表現で、「月のうちの4日目」であることを「of」で表しています。
the year of his birth
彼の生まれた年
→ 「彼が生まれた年」という意味で、「birth(誕生)」という名詞に関連付ける形で「of」が使われています。
補足:この「of」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この数値や時間に関する「of」の用法では、以下のような語と一緒に使われることが多いです。
- kilos/grams/liters/pounds of ~
例:3 liters of juice(ジュース3リットル) - percent/increase/decrease of ~
例:a decrease of 10 percent(10%の減少) - girl/boy/man/woman of ~(年齢)
例:a man of 30(30歳の男性) - the nth of 月名
例:the 21st of June(6月21日) - the year/season/month of ~
例:the summer of 2020(2020年の夏)
これらは日常英語からビジネス、学術文書まで幅広く使われる表現です。英語を学ぶうえで避けて通れない基本的な文型の一つといえるでしょう。
まとめ
使い方6では、前置詞「of」が数値や時間・年齢・日付などの情報を名詞に関連づける方法を学びました。この表現は英語の中で頻出であり、正確な情報を伝える際に非常に役立ちます。
使い方7:一部を示すときの「of」
この使い方の「of」は、**「全体の中の一部」や「限定されたグループの中から特定のもの」**を示すときに用いられます。特に、「some(いくつか)」「a few(少し)」「most(大部分)」「all(すべて)」などの限定詞や数量詞の後に続けて使われます。
この構文を使うことで、「どれぐらいか」「どの部分か」という情報を的確に相手に伝えることができます。また、文の対象を明確にしながら、柔軟な表現が可能になります。
例文と解説
some of his friends
彼の友人のうちの何人か
→ 「some of ~」は「~の中のいくつか・何人か」を意味します。この場合、「his friends(彼の友人たち)」の中の一部を指しています。
a few of the problems
その問題のうちのいくつか
→ 「a few of ~」も同様に、限定された問題群の中の一部を示します。数としては「少数」ですが、具体性が増しています。
the most famous of all the stars
すべてのスターの中で最も有名な人
→ 「the most famous of ~」の構文では、「最上級+of」で「~の中で最も~な」という意味になります。比較の対象が明確になるのが特徴です。
none of us
私たちの誰一人として
→ 否定の形「none of ~」もよく使われます。「us(私たち)」の中の誰にも当てはまらない、という意味になります。
each of the students
その学生たち一人一人
→ 「each of ~」は、「~のそれぞれ」を表し、複数ある中から個別に見るニュアンスがあります。
補足:この「of」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この用法では、「全体の中の一部や特定の対象」を指す限定詞や数量詞と一緒に使われます。以下はよく見られるパターンです。
- some of + 名詞
例:some of the books(本のうちの何冊か) - most of + 名詞
例:most of the time(時間のほとんど) - all of + 名詞
例:all of them(彼ら全員) - none of + 名詞
例:none of the answers(どの答えも~ない) - each of + 名詞
例:each of the students(学生たちそれぞれ) - many/few/several of + 名詞
例:many of my friends(私の友人の多く)
このパターンは、会話でも文章でも頻繁に登場する重要表現です。特に TOEIC や英検などの試験にもよく出てくる構文ですので、しっかり覚えておきたいところです。
まとめ
使い方7では、前置詞「of」が「全体の中の一部」を表す用法であることを解説しました。この構文は、特定のグループや対象を明示することで、英語でのコミュニケーションにおける明確さを高めてくれます。
使い方8:位置や時間を示す「of」
この使い方では、「of」は空間的または時間的な関係性を表すために使われます。特定の出来事の時期や、ある地点からの距離・方角を明確にする際に使われるのが特徴です。
たとえば、「just north of Tokyo(東京のすぐ北)」のように、地理的な位置を相対的に表現する場面や、「at the time of the war(戦争の時に)」のように歴史的な時間軸を示す場面などがあります。英語では、「~のそば・付近」「~のとき」といった意味合いを持つ非常に便利な使い方です。
例文と解説
just north of Detroit
デトロイトのすぐ北
→ 「of」は「デトロイト」を基準として、その北側に位置することを示しています。「just」が付くことで「すぐに」というニュアンスが加わります。
a little south of the city center
市の中心部の少し南
→ こちらも同様に、「the city center(市の中心部)」から見た相対的な位置(南側)を表しています。
at the time of the revolution
革命の時に
→ 「the time of ~」という形で、ある出来事の期間や瞬間を特定しています。歴史の出来事や過去の状況を語るときによく使われます。
the morning of her wedding
彼女の結婚式の朝
→ 「of」は「彼女の結婚式」に関する「朝」という具体的な時間を特定しています。「時間+of+名詞」で、その時間がどんな出来事に属しているかを明示できます。
補足:この「of」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この用法の「of」は、地理的位置や特定の時期・出来事を表す名詞と一緒に頻繁に使われます。以下に例を挙げます。
- 方角+of + 地名 - north of Tokyo(東京の北) - west of London(ロンドンの西)
- time of + 出来事 - time of the festival(祭りの時期) - time of the accident(事故が起きたとき)
- morning/evening/day/week/year + of + 名詞 - the day of the ceremony(式の日) - the week of the election(選挙の週)
このような組み合わせは、会話でもニュースでも非常に広く用いられており、背景や状況を具体的に説明するのに最適な表現です。
まとめ
使い方8では、「of」を用いた空間的・時間的な関係性の表現に焦点を当てました。英語では、方角・位置・時間を相対的に示す際にこの「of」が非常に役立ちます。
使い方9:動詞由来の名詞とセットで使う「of」(The noun after ‘of’ can be either the object or the subject of the action.)
この使い方では、「of」は動詞から派生した名詞(動名詞や抽象名詞)と共に使われることが多く、動作の主語や目的語を明示する働きをします。
たとえば、「arrival(到着)」や「criticism(批判)」など、動作を表す名詞のあとに「of + 名詞」を続けることで、「誰が何をした(された)のか」という文の構造的な役割を担います。
これは、英語の中でも非常に重要な構文のひとつで、学術的な文章やニュース、ビジネス文書などのフォーマルな場面で頻出する表現です。
例文と解説
the arrival of the police
警察の到着
→ 「arrival(到着)」という動作を誰が行ったかを「of the police(警察が)」で示しています。この場合、「警察が到着した」という意味になります。
criticism of the police
警察に対する批判
→ こちらは「criticism(批判)」を「of the police(警察に対する)」で修飾しています。つまり、「誰に向けた批判なのか」を示しています。
the howling of the wind
風のうなり声
→ 「howling(うなること)」という動作が「wind(風)」によって引き起こされているという意味です。自然現象を描写するときによく使われます。
fear of the dark
暗闇への恐怖
→ 「fear(恐怖)」という感情が「the dark(暗闇)」に対して向けられていることを示しています。
このように、「of」の後に続く名詞が、その動作や感情の対象または原因であることを表すのがこの使い方の特徴です。
補足:この「of」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この構文では、主に動作や感情を表す名詞と一緒に用いられます。以下のような単語と「of」がセットになることが多いです。
- arrival of ~(~の到着)
- departure of ~(~の出発)
- criticism of ~(~への批判)
- praise of ~(~への称賛)
- fear of ~(~への恐怖)
- memory of ~(~の記憶)
- sound of ~(~の音)
- crying of ~(~の泣き声)
例文:
- The memory of his smile still lingers.
彼の笑顔の記憶はいまだに残っている。 - The sound of rain was soothing.
雨の音は心を落ち着かせた。
この用法を理解することで、抽象的な文章や感情の描写が格段に豊かになります。
まとめ
使い方9では、「動詞由来の名詞 + of + 名詞」という形で、動作の主体や対象を表す方法を学びました。この構文は、表現力を上げたい学習者にとって非常に有益なツールであり、英作文や読解のレベルを引き上げてくれます。
使い方10:動詞の後に置かれ、動作に関わるもの・人を示す「of」
この用法では、「of」は特定の動詞とともに使われ、行為や状態に関係する「対象」や「原因」などを示す働きをします。多くの場合、「deprive(奪う)」「think(考える)」「clear(無罪とする)」といった、意味上で「~を〜から」や「~に対して」などの関係性を含む動詞に続きます。
この構文では、
▶「動詞 + 人 + of + 物(または状態)」の形で「人から~を奪う・除く」などの意味になります。
▶また、「think of ~(~のことを考える)」のように句動詞的に使われるものもあります。
例文と解説
to deprive somebody of something
誰かから何かを奪う
例:The accident deprived him of his eyesight.
その事故は彼から視力を奪った。
→ 「deprive A of B」で「AからBを奪う」という構文。
「of」は「奪われる対象(=B)」を導きます。
to clear somebody of something
誰かを〜の嫌疑から晴らす
例:She was cleared of all charges.
彼女はすべての容疑を晴らされた。
→ ここでも、「of」は「取り除かれる対象(容疑)」を指しています。
to think of something
何かを考える/思い浮かべる
例:Think of a number between 1 and 10.
1から10の間で数字を一つ考えてください。
→ 「think of」は「~について考える・思い浮かべる」という意味の句動詞です。
to remind somebody of something
誰かに〜を思い出させる
例:This song reminds me of my childhood.
この曲は私に子ども時代を思い出させる。
→ 「of」は、「思い出されるもの・内容」を導きます。
補足:この「of」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この使い方では、以下のような特定の動詞とセットになることが多いです。文法的に決まった形なので、そのまま覚えておくのが効果的です。
- deprive A of B(AからBを奪う)
- rob A of B(AからBを奪う)
- cure A of B(AのBを治す)
- clear A of B(AのBの嫌疑を晴らす)
- convince A of B(AにBを納得させる)
- remind A of B(AにBを思い出させる)
- inform A of B(AにBを知らせる)
- think of B(Bについて考える)
例文:
- He was robbed of his wallet.
彼は財布を奪われた。 - The treatment cured her of the disease.
その治療が彼女の病気を治した。
これらは、英検やTOEIC、大学入試などでも頻出の重要表現です。
まとめ
この使い方10では、「of」が動詞とセットになって行為の対象・結果・原因などを表す構文について学びました。こういった「動詞+of+名詞」型の表現は、語彙力をアップさせる鍵となるので、意味と構造のペアで覚えることが効果的です。
使い方11:形容詞の後に使われる「of」
この使い方では、形容詞の後に「of」が使われることによって、感情や意見の対象を表す役割を果たします。特に、感情や評価を示す形容詞が後に続き、「of」の後にはその対象となるものや人が続きます。
この構文は、形容詞 + of + 名詞の形で、感情や評価を表現する際に用いられます。例えば、「proud of(~を誇りに思う)」「ashamed of(~を恥じる)」などのフレーズがよく見られます。
例文と解説
to be proud of somebody/something
~を誇りに思う
例:She is very proud of her achievements.
彼女は自分の業績を非常に誇りに思っている。
→ ここでは、形容詞「proud(誇りに思う)」が「of」を介して、誇りに思っている対象(この場合は「her achievements」)を示しています。
to be ashamed of somebody/something
~を恥じる
例:He was ashamed of his behavior.
彼は自分の行動を恥じていた。
→ 「ashamed of」は、「恥じる」という感情を示すフレーズで、対象は「his behavior(彼の行動)」です。
to be afraid of something
~を恐れる
例:She is afraid of spiders.
彼女はクモを恐れている。
→ 「afraid of」もよく使われる形容詞+「of」のセットで、ここでは「spiders」が恐れる対象となっています。
to be capable of something
~をする能力がある
例:He is capable of doing great things.
彼は素晴らしいことをする能力がある。
→ 「capable of」では、「of」の後に「doing great things(素晴らしいこと)」という動作が続きます。
補足:この「of」はどんな言葉とよく組み合わさる?
「形容詞 + of」のセットとしてよく使われる表現を覚えておくと、英会話やライティングでの表現力が増します。以下に代表的な形容詞の組み合わせを挙げます。
- proud of(~を誇りに思う)
- ashamed of(~を恥じる)
- afraid of(~を恐れる)
- capable of(~をする能力がある)
- fond of(~が好き)
- tired of(~に飽きる)
- aware of(~を認識している)
- jealous of(~に嫉妬する)
例文:
- I’m fond of reading.
私は読書が好きです。 - She is aware of the risks.
彼女はそのリスクを認識しています。 - He’s jealous of his colleague’s success.
彼は同僚の成功に嫉妬している。
まとめ
この使い方11では、形容詞の後に「of」を使って感情や意見の対象を示す構文について学びました。これらのフレーズは日常的にもよく使われ、感情を表現する際に非常に便利です。形容詞+「of」のセットで覚えることで、英語力がさらに向上します。
使い方12:「人の行動に対する意見」を表すof
この用法の「of」は、人の行動や態度について話すときに、その行為に対する話し手の評価や意見を述べる目的で使われます。たとえば「It was kind of you to〜」のように、「あなたが〜してくれて親切だった」というような意味を表現する際に使われます。
この「of」は形容詞(kind, nice, generous, rude など)と組み合わされ、その行動がどんな性質を持つかを主観的に評価します。文構造としては、It is + 形容詞 + of + 人 + to + 動詞の原形というパターンが基本形です。フォーマルな表現や丁寧な物言いをするときに重宝される構文でもあります。
例文と解説
It was kind of you to offer help.
手を貸してくれるなんて、あなたは親切ですね。
→「kind」が話し手の評価で、「of you」が「あなたの行動」に対して使われています。
It was rude of him to interrupt the meeting.
会議を遮るなんて、彼は失礼でした。
→「rude」というネガティブな評価に「of him」が加わることで、彼の行為が失礼だったと述べています。
It was generous of Sarah to donate so much money.
多額の寄付をしてくれるなんて、サラは寛大でした。
→「generous of Sarah」は、サラの行動に対する高い評価を示しています。
It’s careless of you to leave the door open.
ドアを開けっぱなしにするなんて、不注意ですね。
→この文では「careless」がその行動の性質として使われています。
この構文は、丁寧に相手の行動に感謝や非難を伝えるのに最適です。また、書き言葉やフォーマルな場面で好まれるため、英作文でも評価されやすい表現です。
補足:この「of」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この用法の「of」は、以下のような評価系形容詞とよくセットで使われます。形容詞の意味が、そのまま行動の性質の評価に直結します。
よく使われる形容詞+ofの例:
- kind of(親切な)
It was kind of her to stay and help. - nice of(優しい、親切な)
It’s nice of you to visit me. - generous of(寛大な)
That was generous of them to pay for dinner. - rude of(失礼な)
It was rude of him not to reply. - careless of(不注意な)
It was careless of you to forget the appointment. - silly of(愚かな)
It was silly of me to believe that story.
このように、形容詞の選び方によってポジティブにもネガティブにもなります。その人の行為について評価するのが目的であるため、形容詞は感情や判断に関わるものが多く使われます。
まとめ
今回取り上げた「of」の使い方は、英語で人の行動を評価するときにとても便利な表現です。
「It is 形容詞 of 人 to ~」という構文を覚えておけば、相手の行動に対する気持ちを丁寧かつ正確に伝えることができます。
この表現は感謝、非難、称賛、注意喚起など、多様な感情を表すのに使える万能構文です。英会話やライティングにおいても応用が利きますので、ぜひ自分の言葉として使いこなせるようにしてみてください。
使い方13:「of」が名詞を強調する用法
最後の使い方は、名詞の直前に「of」が使われ、名詞が何かの特徴や性質を強調するというものです。この使い方では、通常「of」の後に来る名詞が主語を修飾する形で、強調の役割を果たします。
この場合、特に否定的または強調的な意味を持つことが多く、「of」がその名詞を際立たせるために使われます。英語ではしばしば、特定の性質や特徴を表現する際に「of」を使います。
例文と解説
Where’s that idiot of a boy?
あのバカな男の子はどこにいるのか?
例:Where’s that idiot of a boy who always causes trouble?
いつもトラブルを起こすあのバカな男の子はどこにいるのか?
→ ここで「idiot of a boy」は「バカな男の子」という意味で、通常の「idiot」よりも強調された表現です。「of a boy」によって、その人物が持つ特性を強調しています。
What a fool of a man!
なんて愚かな男なんだ!
例:What a fool of a man to leave his keys at home!
鍵を家に忘れてきたなんて、なんて愚かな男なんだ!
→ 「fool of a man」は「愚かな男」と訳され、通常の「fool」よりもその性格や行動が強調されています。
補足:この「of」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この用法で「of」をよく使う表現は、否定的な評価を伴うことが多いため、特定の形容詞や名詞とセットで使われます。以下はそのいくつかの例です。
- a fool of a man(愚かな男)
- an idiot of a person(バカな人)
- a monster of a machine(ものすごく大きな機械)
- a coward of a soldier(臆病な兵士)
- a hero of a man(英雄的な男)
- a devil of a woman(ひどい女)
例文:
- She’s a devil of a woman who always speaks her mind.
彼女は常に自分の考えをはっきり言う、ひどい女だ。 - He’s a fool of a man for not realizing the truth.
彼は真実に気づかなかった愚かな男だ。
まとめ
今回の使い方13では、「of」が名詞を強調する役割を果たす場合について学びました。特に、その人物や物事の特性や性質を強調するために使われます。この構文は、特に否定的な意味合いを持つことが多いため、強い印象を与えることができます。
前置詞「of」のさまざまな使い方を理解し、英語での表現力を高めていきましょう!
この記事を書いた人

- イギリス人で英語と日本語のバイリンガルです!言語が大好きなので、毎日日本語を勉強しています。日本人があまり知らないネイティブ表現を紹介できれば嬉しいです。
最新の投稿
 イギリス英語2025年5月14日come up withの意味と使い方を例文で紹介
イギリス英語2025年5月14日come up withの意味と使い方を例文で紹介 ネイティブ表現2025年5月13日ネイティブの英文で英語表現を覚えよう! 050 I’m tired of all those success stories. Here is my Real Startup Story!! #2
ネイティブ表現2025年5月13日ネイティブの英文で英語表現を覚えよう! 050 I’m tired of all those success stories. Here is my Real Startup Story!! #2 ネイティブ表現2025年5月13日ネイティブの英文で英語表現を覚えよう! 050 I’m tired of all those success stories. Here is my Real Startup Story!!
ネイティブ表現2025年5月13日ネイティブの英文で英語表現を覚えよう! 050 I’m tired of all those success stories. Here is my Real Startup Story!! ネイティブ表現2025年5月13日ネイティブの英文で英語表現を覚えよう! 048 Cash buyers – turns out doesn’t have cash until summer now
ネイティブ表現2025年5月13日ネイティブの英文で英語表現を覚えよう! 048 Cash buyers – turns out doesn’t have cash until summer now