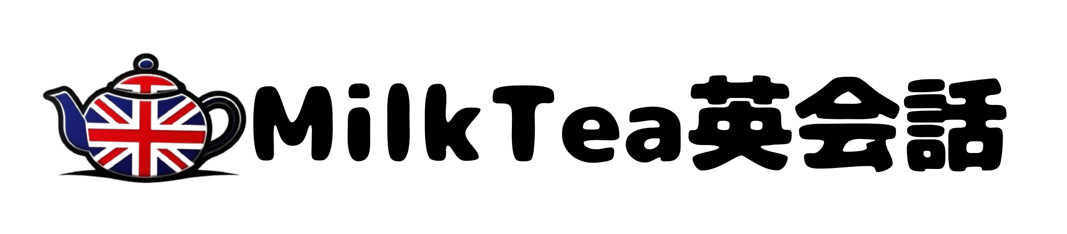【完全攻略】前置詞 to の意味と使い方を徹底解説!例文でニュアンスも完璧マスター

英語における基本前置詞「to」は、日常会話からビジネス英語、ライティングまであらゆる場面で使われる超重要単語です。一見シンプルに見えるこの前置詞ですが、実は意味や使い方が多岐にわたります。本記事では、Oxford Learner’s Dictionariesの定義に基づき、「to」の多様な用法を一つずつ丁寧に解説していきます。
- 使い方1:in the direction of something; towards something(〜の方向へ、〜に向かって)
- 使い方2:as far as something(〜まで)
- 使い方3:to the [方向] of something(〜の[方向]にある)
- 使い方4:〜に、〜へ(受け手を示す)
- 使い方5:範囲・期間の終わりを示す「〜まで」
- 使い方6:「〜前」を表す to(before the start of something)
- 使い方7:ある状態に至る「〜という状態に変わる to」
- 使い方8:動作の影響を受ける対象を示す「to」
- 使い方9:2つのものが接続・結合されていることを示す「to」
- 使い方10:人・物同士の関係性を示す「to」
- 使い方11:「〜への」という意味の「to」(directed towards; in connection with)
- 使い方12:比率や比較の後半を導入する「to」
- 使い方13:数量や率を示す「to」
- 使い方1 4「in honour of(〜を讃えて)」の使い方
- 使い方15:態度・反応を示す「to」
- 使い方1 6「意見や感覚を表す用法」
- 使い方17:同時進行・同伴の状況を表す「to」
- 使い方18:動作の目的「〜に向けて与える意図」の「to」
使い方1:in the direction of something; towards something(〜の方向へ、〜に向かって)
この使い方では、「to」は「〜に向かって」「〜の方向へ」といった意味で、動作や動きが特定の場所や方向に向かうことを表します。移動の目的地や目指す方向を明確にするために使われるのが特徴で、最も基本的かつよく使われる用法の一つです。「go to school」「walk to the station」など、日常的な場面で頻出します。
例文と解説
I walked to the office.
私はオフィスに向かって歩いた。
- 「to the office」は「オフィスという目的地に向かって」という意味を明確にしています。
- 「walk」は移動を伴う動詞なので、「to」と相性が非常に良いです。
It fell to the ground.
それは地面に落ちた。
- 「to the ground」は、落ちた先が「地面」であることを示しています。
- 動作の方向・到達点を示す役割です。
It was on the way to the station.
それは駅に向かう途中にあった。
- 「to the station」が目的地で、「on the way to」で「〜へ向かう途中で」を意味します。
- 「on the way to + 場所」はセットで覚えておきたい便利表現です。
He’s going to Paris.
彼はパリに向かっているところだ。
- 「go to + 地名」で「〜に行く」というシンプルな構文。
- このように都市名や国名と非常によく使われます。
My first visit to Africa.
私のアフリカへの初めての訪問。
- 「visit to + 場所」で「〜への訪問」を意味します。
- 抽象的な表現にも「to」は自然に使われます。
He pointed to something on the opposite bank.
彼は向こう岸にある何かを指差した。
- 「point to」は「〜を指差す」という意味の定型表現。
- この場合も「to」は方向や対象を示しています。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この「to」は、「移動」「指示」「方向」などを示す動詞や名詞とよく組み合わされます。以下に代表的なコロケーション(語の組み合わせ)を挙げます。
- go to school(学校に行く)
- come to the station(駅に来る)
- move to London(ロンドンに引っ越す)
- point to the sky(空を指差す)
- send to someone(誰かに送る)
- travel to Japan(日本に旅行する)
「to + 地名」や「to + 名詞」は非常に使いやすく、英会話の中で頻出する表現です。また、「on the way to」や「my trip to」など、定型表現も多いのでセットで覚えると表現の幅が一気に広がります。
使い方1 まとめ
この「to」の用法は、「目的地」や「到達点」、「方向性」を明示する働きがあります。最も基本的で汎用性の高い意味であるため、初級から上級まであらゆるレベルで使われます。動作の方向を表す英語表現の基礎として、しっかりマスターしておきましょう。
使い方2:as far as something(〜まで)
この用法の「to」は、物理的な距離や長さ、または空間的な広がりの終点・到達点を表すときに使われます。目的地に向かう動きではなく、単純に「どこまで続いているか」を表すのが特徴です。距離に限らず、「髪の長さ」や「川の位置」など、目に見える範囲の終わりまでを示したいときに非常に便利です。
例文と解説
The meadows lead down to the river.
その草原は川まで続いている。
- 「lead down to」は「〜へと続く」「〜に向かって傾斜している」という意味の表現。
- ここでは、草原の広がりが「川まで」という終点を持っていることを示しています。
Her hair fell to her waist.
彼女の髪は腰まで垂れていた。
- 「fell to her waist」は、「髪の長さが腰まである」ことを描写しています。
- 身体の部位などを使って長さを説明する際によく使われます。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この使い方の「to」は、以下のような表現とよく組み合わされます:
- to the river(川まで)
- to the end(端まで)
- to the top(頂上まで)
- to the bottom(底まで)
- to the wall(壁まで)
- to the waist(腰まで)
また、「lead to(〜へと続く)」「stretch to(〜まで伸びる)」「reach to(〜に達する)」といった動詞とセットになることが多く、物の広がりや長さを描写する際に頻繁に使われます。
使い方2 まとめ
この「to」は、空間的・物理的な「終点」や「到達点」を明示する役割を持っています。移動や動作というよりも、「どこまで続いているか」「どこまで伸びているか」を表すため、風景描写や身体的な特徴の描写など、特定の範囲を正確に示すのに非常に有効です。
使い方3:to the [方向] of something(〜の[方向]にある)
この用法では、前置詞「to」が基準となる場所から見た方角や位置関係を示すために使われます。「〜の北に」「〜の左に」など、空間的な配置や相対位置を表現する際に使われる非常に便利な表現です。地図の説明や道案内、視覚的な説明文において頻出します。
例文と解説
Place the cursor to the left of the first word.
最初の単語の左側にカーソルを置いてください。
- 「to the left of」は「〜の左側に」を意味し、パソコン操作や視覚的な配置を説明する際に便利です。
- 「of the first word」のように、基準となる対象を明確にするのがポイント。
There are mountains to the north.
北の方角に山々がある。
- 「to the north」で「北の方角に」という意味。
- 方角を表すときには、「to the east」「to the west」「to the south」なども同様に使えます。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この用法の「to」は、方角や位置を示す語とよく使われます。以下のようなコロケーションが代表的です:
- to the left of(〜の左に)
- to the right of(〜の右に)
- to the north of(〜の北に)
- to the south of(〜の南に)
- to the east of(〜の東に)
- to the west of(〜の西に)
このように、基準となるものに対する相対的な位置を説明する表現として欠かせない用法です。特に英語の地理・地図に関する表現や、視覚的なガイドでは必須となる構文です。
使い方3 まとめ
この用法では、「to」は空間的・地理的な方角・位置関係を表す前置詞として機能します。「〜の方向に位置している」「〜のすぐ横にある」といった表現を自然に伝えることができ、英語での説明力を格段に高めてくれる構文です。特に旅行・案内・IT系の操作説明で多用されるので、しっかりとマスターしておきましょう。
使い方4:〜に、〜へ(受け手を示す)
この用法の「to」は、**行為の対象(受け手)**を示すときに使われます。誰に対して何かを「渡す」「伝える」「感謝する」など、動作や感情が向かう先を明確にする重要な役割を担います。特に「give」「say」「send」「explain」など、授与・伝達・感情表現の動詞とよく一緒に使われます。
例文と解説
He gave it to his sister.
彼はそれを妹にあげた。
- 「give A to B」は「AをBに与える」という構文。
- 「to his sister」が受け手を明示しています。
I’ll explain to you where everything goes.
どこに何があるのか、あなたに説明します。
- 「explain to 人」で「人に説明する」という定番表現。
- 「explain 人 something」は文法的にNGなので、「to」は必須です。
I am deeply grateful to my parents.
私は両親に深く感謝しています。
- 「grateful to 人」で「〜に感謝している」。
- 感情の対象(感謝の向け先)を示すときにも「to」が使われます。
Who did she address the letter to?
彼女はその手紙を誰に宛てたのですか?
- 「address A to B」で「A(手紙など)をBに宛てる」。
- 受取人や宛先を示す典型的な構文です。
(formal) To whom did she address the letter?
(形式ばった表現)彼女はその手紙をどなたに宛てたのですか?
- フォーマルな場では「to whom」の語順で始めます。
- ビジネス英語や正式な文章で使われる表現です。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この受け手を示す「to」は、以下のような動詞や表現と非常によく使われます:
- give A to B(AをBにあげる)
- send A to B(AをBに送る)
- explain to someone(〜に説明する)
- write to someone(〜に手紙を書く)
- talk to someone(〜に話しかける)
- be nice to someone(〜に親切にする)
- say something to someone(〜に何かを言う)
対象となる人や物への感情・情報・物理的なモノの伝達には、必ずと言っていいほど「to」が登場します。
使い方4 まとめ
この用法は、行為や感情の「向け先」を示す非常に大切な役割を持っています。特に「give」「say」「explain」など、英語の基本動詞とともに使われるため、日常英会話・ビジネス・ライティングすべての場面で必須の知識です。英語らしい表現の核となる構文が多く含まれているので、この用法はしっかりと定着させておきたいですね。
使い方5:範囲・期間の終わりを示す「〜まで」
この用法の「to」は、**数値や時間、種類などの「範囲の終点」**を明示するときに使われます。「〜から〜まで」と言いたいとき、英語では「from A to B」の形で使うのが基本です。期間や数の範囲、リストの開始から終了、年齢の幅、音楽のジャンルなど、**様々なものの範囲の「終わり」**を示すのに欠かせない前置詞です。
例文と解説
a drop in profits from $105 million to around $75 million
利益が1億500万ドルから約7,500万ドルまで減少した。
- 「from A to B」の構文で、**範囲の開始(A)と終了(B)**を示す典型例。
- 金額や統計データで頻出するパターン。
I’d say he was 25 to 30 years old.
彼は25歳から30歳くらいだと思う。
- 年齢の幅を表すときの定番表現。
- 「25 to 30」で「25歳から30歳まで」という意味になります。
I like all kinds of music from opera to reggae.
私はオペラからレゲエまで、あらゆる種類の音楽が好きです。
- 音楽ジャンルの範囲を示しています。
- 「from A to B」の形で、広いジャンルの幅を自然に表現できます。
We only work from Monday to Friday.
私たちは月曜日から金曜日までしか働きません。
- 曜日やスケジュールの範囲でよく使われます。
- ビジネス文書や説明文でよく見かける表現です。
I watched the programme from beginning to end.
私はその番組を最初から最後まで見た。
- 時間の経過を表す際の「始まりから終わりまで」。
- 「from beginning to end」は定番の表現として覚えておくと便利です。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この範囲の終点を示す「to」は、以下のような表現と頻繁に組み合わされます:
- from A to B(AからBまで)
- 10 to 20(10から20まで)
- January to March(1月から3月まで)
- Monday to Friday(月曜から金曜まで)
- beginning to end(始めから終わりまで)
- top to bottom(上から下まで)
また、「to」の前に来る単語には、from / start / range / extend など、範囲や開始を意味する語が多いのが特徴です。
使い方5 まとめ
この用法では、**時間・金額・年齢・範囲などあらゆる「終点」**を示す役割を担っています。「from A to B」の構文は、英語の論理的な説明や情報整理の基盤となるため、正確に使いこなせると文章力が大きく向上します。数字や時間を扱うすべての場面において、この「to」の使い方は必要不可欠です。
使い方6:「〜前」を表す to(before the start of something)
この用法の「to」は、時間に関する文脈で「ある時刻・出来事の直前」を表すときに使います。特に、「○時○分前」を表すときに、英語では“to”を使って時刻を逆算する表現が頻繁に使われます。この形式は特にイギリス英語で多用されるため、英国生活やブリティッシュイングリッシュに親しむ方には欠かせない用法です。
例文と解説
How long is it to lunch?
昼食まであとどれくらい?
- 「to lunch」は「昼食の時間まで」を意味します。
- イベントや予定の始まりまでの残り時間を表す便利な表現。
It’s five to ten.(※特にイギリス英語)
10時5分前です。
- 「five to ten」は「10時まであと5分」を意味します。
- アナログ時計を見ながら時間を表すときの典型的な言い方。
- アメリカ英語では「nine fifty-five」のように表現することも多いですが、イギリス英語ではこの「to」構文が定番です。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この「to(〜前)」の用法では、以下のような語句とセットで使われるのが一般的です:
- five to ten(10時5分前)
- ten to six(6時10分前)
- quarter to eight(8時15分前)
- minutes to midnight(真夜中の数分前)
- to lunch / to dinner / to the meeting(〜の開始前まで)
特に、「時間+to+時刻」のパターンは会話でも頻出するため、自然な聞き取り・発話にはぜひ習得したい表現です。
使い方6 まとめ
この用法の「to」は、「時間の始まりの直前」を示す際に活躍します。特に時刻を逆算して言うスタイルはイギリス英語で非常に一般的で、時計の読み方や日常会話でスムーズなやりとりを可能にしてくれます。「It’s ten to three(3時10分前)」のような表現をサラッと使えると、ネイティブらしさがグッと増しますよ!
使い方7:ある状態に至る「〜という状態に変わる to」
この用法の「to」は、人や物がある状態へと“変化”・“推移”することを示すときに使われます。物理的な状態変化(例:バラバラになる)、心理的な変化(例:涙を流す)、または抽象的な到達(例:完璧に仕上がる)など、変化のゴール地点を示す役割を果たします。
「to」は方向性を持つ前置詞なので、ここでは“ある状態へ向かって動いていく”というイメージを持つと理解しやすくなります。
例文と解説
The vegetables were cooked to perfection.
その野菜は完璧に調理されていた。
「to perfection」は「完璧な状態に至る」ことを表す定番表現。
「cook to perfection」で「理想的な状態になるまで調理する」。
He tore the letter to pieces.
彼はその手紙をズタズタに引き裂いた。
「to pieces」で「バラバラな状態に」。
状態の変化=「一枚の手紙」→「バラバラな断片」に至るプロセスを示しています。
She sang the baby to sleep.
彼女は赤ちゃんを歌で眠らせた。
「to sleep」は「眠っている状態に至る」。
「sing A to sleep」は「歌ってAを眠らせる」という意味。
The letter reduced her to tears.
その手紙は彼女を泣かせた。
「reduce A to B」は「AをBの状態にする(追い込む)」。
感情的な変化、つまり「冷静な状態」→「涙を流す状態」への変化を「to」で表しています。
His expression changed from amazement to joy.
彼の表情は驚きから喜びに変わった。
「from A to B」の形で、ある感情から別の感情へと移る様子を表現。
「to joy」は変化の終点、つまり“喜びという状態”。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この変化・到達の意味で使われる「to」は、次のような表現とよく組み合わされます:
to perfection(完璧な状態に)
to pieces(バラバラに)
to sleep(眠っている状態へ)
to tears(涙を流す状態へ)
to madness(狂気へ)
to life(命が宿る状態に)
to silence(静寂へ)
また、「change」「reduce」「drive」「bring」「lead」「turn」など、変化を導く動詞とも相性が良いです。
使い方7 まとめ
この用法では、「to」は“変化の終点”や“目標の状態”を示す前置詞です。物事がどんな最終形に至ったか、どんな感情や状態になったのかを示す際に非常に有用です。抽象的な表現が多いため、上級レベルの英語表現にもよく登場します。自然な英語で豊かな描写をするために、ぜひこの「to」の感覚を身につけておきましょう。
使い方8:動作の影響を受ける対象を示す「to」
この用法の「to」は、ある動作が「誰や何に向けて行われ、その結果として影響が及ぶのか」を示すために使われます。文の中で「to+名詞・代名詞」は、その動作の**“被影響者”**の役割を果たし、「誰(何)に対して、何が行われたのか」を明確にします。
この使い方は、日常英会話でも非常に頻出で、無意識に使われることが多いため、しっかりと意味と使いどころを理解しておくことが大切です。
例文と解説
She is devoted to her family.
彼女は家族に献身的です。
- 「be devoted to」で「〜に献身する」。
- この「to」は、影響や思いが向けられている**対象(her family)**を示しています。
What have you done to your hair?
髪に何をしたの?
- ここでの「to」は、動作「done(した)」の結果が及んだ対象が「your hair」であることを示します。
- この表現は、髪型の変化などに驚いた時によく使われます。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この意味の「to」は、以下のような動詞や形容詞とよくセットになります:
- be kind to(〜に優しい)
- do something to(〜に何かをする)
- be devoted to(〜に尽くす)
- happen to(〜に起きる)
- say sorry to(〜に謝る)
- apply pressure to(〜に圧力をかける)
ポイントは、「動作や感情が向けられる対象」に使うということです。特に、「to+人・物」がセットで使われる表現は、英会話の中で自然に使えるようにしておきたいですね。
使い方8 まとめ
この用法の「to」は、「誰(何)に影響が及ぶのか」という動作の受け手・影響を受ける対象を示す前置詞です。目に見える影響から、感情や献身のような抽象的な影響まで、幅広い状況で使用されます。この使い方に慣れると、表現力が一気に豊かになりますよ!
使い方9:2つのものが接続・結合されていることを示す「to」
この用法の「to」は、ある物と別の物が物理的に結びついている、取り付けられている、接触しているといった「接続・連結の関係」を示します。
電線が建物に取り付けられている、ロープが車に結ばれている、などのように、物理的に“〜にくっついている”状態を表すときに用います。
この用法では、「attach」「connect」「fasten」「tie」「stick」などの接続系動詞と一緒に使われるのが特徴です。
例文と解説
Attach this rope to the front of the car.
このロープを車の前部に取り付けてください。
- 「attach A to B」で「AをBに取り付ける」。
- 「to」は、取り付け先(=車の前部)を明確に示します。
The cable is connected to the TV.
そのケーブルはテレビにつながっている。
- 「connect A to B」=AをBに接続する。
- ケーブルのように一方の端が何かに接続されている状態で、toが使われます。
There’s a note stuck to the fridge.
冷蔵庫にメモが貼ってある。
- 「stick A to B」で「AをBに貼り付ける」。
- こちらも、何かが他のものの表面に物理的に接触している様子を描写します。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この「接続・接着」の意味で使われる「to」は、以下のような動詞と頻繁に一緒に使われます:
- attach A to B(AをBに取り付ける)
- connect A to B(AをBに接続する)
- fasten A to B(AをBに固定する)
- tie A to B(AをBに結びつける)
- glue A to B(AをBに接着する)
- nail A to B(AをBに釘で打ち付ける)
- stick A to B(AをBに貼る)
また、日常英会話やマニュアル、DIY、科学実験などでもよく登場する用法です。
使い方9 まとめ
この用法の「to」は、物理的に何かが他のものにくっついている・接続されている関係を示すときに使います。
特に「attach」「connect」「tie」などの動詞と組み合わせて使われることが多く、機械や日用品など、身の回りの場面でとても実用的です。前置詞「to」の“方向性”のイメージを保ちつつ、「どこに結びついているのか」を示すのがこの用法のポイントです。
使い方10:人・物同士の関係性を示す「to」
この用法の「to」は、人や物と他の人・物との間に存在する「関係性」「つながり」「所属」などを示す際に使われます。
関係の種類はさまざまで、**「結婚・地位・所属・所有・関連」**など、多様な文脈で見られます。
「to」は「〜に向かって」という基本イメージを持ちながら、ここでは「〜に属する/〜と関係する」という形で使われ、物理的な移動ではなく、**“概念的な結びつき”**を意味します。
例文と解説
She’s married to an Italian.
彼女はイタリア人と結婚している。
- 「married to」で「〜と結婚している」。
- 相手との法的・社会的な関係性を示す表現。
The Japanese ambassador to France.
駐フランス日本大使。
- 「ambassador to〜」は「〜に派遣された大使」。
- 所属・任命先の国を「to」で示します。
The key to the door.
そのドアの鍵。
- 「key to〜」は「〜のための鍵」。
- 何かにぴったり合う、または使われるものとの機能的関係を示しています。
The solution to this problem.
この問題の解決策。
- 「solution to〜」で「〜に対する解決策」。
- 問題との対応関係・目的のつながりを表します。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この「関係性を示す」用法では、以下のような語と「to」がよくペアで使われます:
- be married to(〜と結婚している)
- the key to(〜の鍵)
- the answer to(〜への答え)
- the solution to(〜への解決策)
- ambassador to(〜への大使)
- introduction to(〜への紹介・入門)
すべて、「to」のあとに来る名詞が、関係を持つ対象や目的となるものである点に注目しましょう。
使い方10 まとめ
この用法の「to」は、「ある人や物が別の人や物に対して持つ関係性や所属」を示す働きをします。結婚関係、職務上のつながり、物と物の機能的関係など、様々な場面で使われ、特に名詞+toの構文で頻出です。
英語で関係を表現する上で非常に重要な用法なので、例文ごと覚えると効果的です!
使い方11:「〜への」という意味の「to」(directed towards; in connection with)
この用法の「to」は、ある感情・行動・表現・影響などが、特定の対象に向かっていることや、それに関連していることを示す前置詞です。
単に「物理的に向かう」という意味ではなく、話題・議論・注目・言及・感情の矛先がどこにあるのかを表現するために使われます。
この「to」は、文中で抽象的な動詞(例えば「threaten」「refer」「reaction」など)と一緒に使われることが多く、フォーマルな場面や書き言葉でもよく見られる使い方です。
例文と解説
It was a threat to world peace.
それは世界平和への脅威だった。
- 「threat to〜」で「〜に対する脅威」。
- 抽象的な対象(world peace)に向けられた行為や状況を示しています。
She made a reference to her recent book.
彼女は最近の著書に言及した。
- 「make a reference to〜」は「〜に言及する」。
- 話題や注目がどこに向いているかを明確に伝える表現。
His comment was offensive to many people.
彼の発言は多くの人々を不快にさせた。
- 「offensive to〜」で「〜に対して不快な」。
- 相手に向けて感情的な影響が及んでいることを示しています。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この用法では、以下のような語と一緒に使われることが多いです:
- threat to(〜への脅威)
- damage to(〜への損害)
- invitation to(〜への招待)
- reference to(〜への言及)
- reaction to(〜への反応)
- solution to(〜への解決策)
- objection to(〜への反対)
これらはすべて、あるものに対して行為・感情・話題が**「向かっている」または「関係している」**という意味を表しています。
使い方11 まとめ
この用法の「to」は、「〜に向かっている」「〜に関連している」という抽象的な方向性や関係性を表す前置詞です。
物理的な移動ではなく、議論や感情、意見の対象がどこに向けられているかを表すのがポイントです。特にニュース、学術論文、スピーチなどで頻繁に使われるため、しっかり理解しておくとワンランク上の表現力が身につきます。
使い方12:比率や比較の後半を導入する「to」
この用法の「to」は、**「比較の後半部分」や「比率におけるもう一方の要素」を導入する際に使われます。
数的な比率や、物事の大小・程度などを比較する文脈で、「A to B(A対B)」という形で登場することが多く、「〜に対して」「〜に比べて」**という訳が自然です。
また、この用法はスポーツの得点、統計、寸法、燃費、意見の比較など、数値的・主観的な比較の両方に使われます。
例文と解説
We won by six goals to three.
6対3で私たちが勝った。
- スポーツのスコアでよく使われる形。
- 「A to B」で「A点対B点」を表す。
I prefer walking to climbing.
私は登るより歩くほうが好きです。
- 「prefer A to B」で「BよりAの方を好む」。
- 好みや意見を比較する際の典型表現。
The industry today is nothing to what it once was.
現在の産業は、かつてのそれとは比べものにならない。
- 「nothing to〜」は「〜に比べものにならない」という意味の決まり文句。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この比較・比率を表す用法では、以下のような語と「to」が頻出です:
- prefer A to B(BよりAを好む)
- compare A to B(AをBに例える・比較する)
- win by X to Y(X対Yで勝つ)
- ratio of A to B(A対Bの比率)
- nothing to(〜に比べものにならない)
特に 「prefer」「nothing」「score」 などの語と共に、比較対象を導く前置詞として使われます。
使い方12 まとめ
この用法の「to」は、比較や比率における後半部分の導入に使われます。
A to B という構文は、日常英語からビジネス・学術的な場面まで広く使われ、好み・評価・数的分析など、さまざまな文脈に対応可能です。
英語学習者にとっては「prefer A to B」のような構文が最もなじみ深く、正確に使いこなすことで、説得力ある意見表現ができるようになります。
使い方13:数量や率を示す「to」
この用法の「to」は、**「〜あたり」や「〜につき」**という意味で使われ、比率や割合、単位あたりの数量を表現する際に用いられます。
日本語の「1リットルあたり○○円」「1ガロンにつき○○マイル」などに相当する表現です。
この用法は特に寸法・燃費・換算・速度・密度などの理系的な話題や、ビジネスや製品の説明などで非常によく使われます。
例文と解説
There are 2.54 centimetres to an inch.
1インチは2.54センチメートルです。
- 単位換算でよく使われる構文。
- 「to」の後に基準単位(この場合は「inch」)がきて、「1単位あたり○○」の形。
This car does 30 miles to the gallon.
この車は1ガロンあたり30マイル走る。
- 「do + 距離 + to the gallon」は「燃費」を表す表現。
- アメリカ英語では日常的に使われる構文。
The ratio of men to women is 3 to 2.
男性と女性の比率は3対2です。
- 「ratio of A to B」で「A対Bの比率」。
- 比較の文脈でもこの「to」は頻繁に使われます。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この数量・率を示す用法では、以下の語と一緒によく使われます:
- miles to the gallon(ガロンあたりのマイル数)
- centimetres to an inch(インチあたりのセンチ)
- people to a room(部屋あたりの人数)
- ratio of A to B(A対Bの比率)
- cost to income ratio(コストと収入の比率)
「to」の直後に来るのは基準単位や母数であり、「〜に対して」の感覚で比率や割合を明確にします。
使い方13 まとめ
この用法の「to」は、単位あたりの数量や比率を示す前置詞で、ビジネスや理系の話題で特に重要です。
「A to B」という形で「A:Bの関係」「BにつきA」と訳せるこの構文を覚えると、数量的な情報を正確に伝える力が飛躍的に向上します。
英語でデータや統計を扱う際には必須の用法ですので、しっかりマスターしておきましょう!
使い方1 4「in honour of(〜を讃えて)」の使い方
「to」が「in honour of」というフレーズと組み合わさることで、「誰かを讃えて」「何かを記念して」という意味を表現します。このフレーズは、特に記念碑や祝賀会、特別な行事でよく使用されます。意味としては、「敬意を表して」「功績を称えて」などの意図を持っています。この用法を使うことで、何か重要な出来事や人物に対する敬意を示すことができます。
例文と解説
1. A monument to the soldiers who died in the war.
戦争で命を落とした兵士たちを讃える記念碑。
→ この例文では、「to」が「monument」と結びつき、「戦争で亡くなった兵士たちを讃えて建てられた記念碑」を示しています。「to」はその対象を指し示し、その行為がどのように記念されるかを表現しています。
2. Let’s drink to Julia and her new job.
ジュリアと彼女の新しい仕事を祝って乾杯しよう。
→ ここでは「to」が「drink」と結びつき、ジュリアの新しい仕事を祝うための乾杯を意味しています。乾杯をする対象や理由を示す際に「to」を使います。この表現は、祝賀の場面で非常によく使われます。
3. The concert was held in honour of the composer’s 100th birthday.
そのコンサートは作曲家の生誕100周年を讃えて開催されました。
→ 「in honour of」によって、「作曲家の生誕100周年」を祝う目的で開催されたことが伝えられています。このように、特定の人物や出来事を讃える目的でイベントや行動を行う際に「to」を使います。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
「to」は特定の人物や出来事を讃える目的で使う際、以下のような単語や表現とよく組み合わさります。
- a monument to(〜を讃えた記念碑)
- 例: a monument to the fallen soldiers(戦死した兵士たちを讃える記念碑)
- a tribute to(〜への賛辞)
- 例: a tribute to the late president(故大統領への賛辞)
- a toast to(〜を祝っての乾杯)
- 例: a toast to our success(私たちの成功を祝っての乾杯)
- dedicated to(〜に捧げられた)
- 例: a song dedicated to love(愛に捧げられた歌)
これらの表現は、特定の人物や出来事を記念したり祝ったりする際に用いられます。「to」を使うことで、何かを称賛する意図が明確に伝わります。
まとめ
前置詞「to」の「in honour of」を使った用法は、特に祝賀や記念、讃える意味を強調する際に役立ちます。人物や出来事を称賛し、尊敬の意を示すために広く使用される表現です。日常的な祝賀の場面から、歴史的な出来事の記念に至るまで、幅広く活用できるこの用法を理解することで、英語表現がより豊かになります。
使い方15:態度・反応を示す「to」
この用法の「to」は、ある出来事や状況に対する人の反応・態度を表すときに使われます。
日本語で言えば、「〜に対して驚いた」「〜に冷たい態度をとった」といった表現が近く、感情や態度の矢印が「to」の後ろの対象に向かっているのがポイントです。
使われる文の主語は多くの場合、人(または感情を持つ主体)であり、**「to + 名詞(出来事・事実・行動など)」**の形になります。
例文と解説
To her astonishment, he smiled.
彼女が驚いたことに、彼は微笑んだ。
- 「To her astonishment」は「彼女が驚いたことには」。
- 慣用表現のように文頭に置かれて、「驚きの対象となった行動」を導きます。
His music isn’t really to my taste.
彼の音楽は、私の好みにはあまり合わない。
- 「to my taste」は「私の好みに合う」。
- 「好み」「印象」「反応」を表す場面で使われる頻出のフレーズ。
Her response to the criticism was calm and measured.
その批判に対する彼女の反応は冷静で落ち着いていた。
- 「response to〜」は「〜に対する反応」。
- このように「名詞+to」で「〜に対しての〜」という構文が完成します。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この用法の「to」は、感情や反応を表す語とよく一緒に使われます:
- to one’s surprise / dismay / relief / joy(〜の驚き/落胆/安堵/喜びに)
- to my taste / liking(私の好みに)
- reaction / response / attitude to(〜に対する反応/態度)
- kind to / cruel to(〜に親切/〜に残酷)
つまり、「人の内面(気持ち・反応)」を表現したいときに非常に役立つ用法です。
使い方15 まとめ
この「to」は、誰かが何かにどのように反応したか・どんな態度を取ったかを明確にする際に欠かせない表現です。
英語では「感情の方向性」を示す前置詞として「to」が使われることが多く、「喜び」「驚き」「好み」などの個人の主観的な感じ方や対応を語る際には必須の構文と言えます。
とくに「To my surprise」や「to my taste」のような表現は、そのまま覚えておくと洗練されたナチュラルな英語表現として会話でもライティングでも重宝します。
使い方1 6「意見や感覚を表す用法」
「to」は、特に何かの感覚や他者の意見を示すときに使用されます。この用法では、話し手の感覚や感情が中心に置かれ、「何かがどのように聞こえる、見える、感じられる」といった形で表現します。この使い方を理解することで、より自然で柔軟な英語表現が可能になります。
例文と解説
1. It sounded like crying to me.
それは私には泣いているように聞こえました。
→ この例文では、「to me」を使って、話し手の感じ方や意見を強調しています。「to」は「me(私)」と結びつけられており、話し手の視点を示しています。ここで「to」は、話し手が他の人とは違った感覚を持っていることを示しており、感覚的な意見や印象を表現するために使われます。
2. Her explanation seemed confusing to us.
彼女の説明は私たちには混乱しているように思えました。
→ この場合、「to us」が「私たちにとって」を意味し、話し手が特定のグループ(ここでは「私たち」)の感覚や印象を表現しています。「to」を使うことで、他者の視点を反映させている点がポイントです。
3. The music felt soothing to her.
その音楽は彼女にとっては心地よく感じられました。
→ 「to her」が示すのは、音楽を聴いている「彼女」の感覚です。このように、「to」を使って対象者の感覚を表現することができます。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
「to」は、感覚や意見を示す際に、以下のような単語やフレーズとよく組み合わさります。
- seem to(〜のように見える)
- 例: The idea seemed to make sense to me.(そのアイデアは私には理にかなっているように思えた。)
- sound to(〜のように聞こえる)
- 例: The song sounded familiar to him.(その歌は彼には馴染みのあるもののように聞こえた。)
- feel to(〜のように感じる)
- 例: The fabric feels soft to the touch.(その生地は触ると柔らかく感じる。)
- look to(〜のように見える)
- 例: The painting looks abstract to me.(その絵は私には抽象的に見える。)
- seem like(〜のように見える)
- 例: The explanation seems like a good solution to me.(その説明は私には良い解決策のように見える。)
これらの組み合わせを使うことで、感覚的な意見や印象を表現することができ、より多彩な英語表現が可能になります。
まとめ
前置詞「to」は、意見や感覚を表す際に非常に重要な役割を果たします。この用法では、話し手の視点や感覚を強調することで、印象や感じ方を伝えることができます。特に「to」が示す対象に注意を払いながら使うことで、英語の表現力が豊かになり、相手に伝わりやすいコミュニケーションが可能になります。
使い方17:同時進行・同伴の状況を表す「to」
この用法の「to」は、何かが行われている最中に起きた出来事や、背景にある状況を表すときに使われます。
特にスピーチや舞台、演奏、拍手など、出来事と出来事が「同時に起きている」ことを示すのが特徴です。
「to + 名詞」の形で、「〜の最中に」「〜を背景にして」「〜と共に」といったニュアンスを表現できます。
場面描写や文芸的な表現にもよく登場する、少しフォーマルまたは文学的な響きを持つ用法です。
例文と解説
He left the stage to prolonged applause.
彼は盛大な拍手の中、ステージを後にした。
- 「to prolonged applause」は「長い拍手の中で」。
- 「to」は「拍手とともに」「拍手を受けながら」という同時進行のニュアンスを持つ。
She accepted the award to a standing ovation.
彼女はスタンディングオベーションを受けながら賞を受け取った。
- 「to a standing ovation」で「スタンディングオベーションと共に」。
- 状況の華やかさや感動を強調する表現。
He walked in to the sound of violins.
彼はバイオリンの音に包まれて入ってきた。
- 「to the sound of〜」は「〜の音と共に」。
- 「音」や「歓声」「音楽」などと一緒に使われやすいパターン。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この用法の「to」は、音・拍手・反応・背景的な要素と一緒に使われることが多いです:
- to applause(拍手とともに)
- to cheers(歓声の中で)
- to music / the sound of violins(音楽と共に/バイオリンの音にのせて)
- to a standing ovation(スタンディングオベーションを受けながら)
- to laughter(笑いに包まれて)
主にイベントや演出、感情的な場面を描写する英語で重宝される表現です。
使い方17 まとめ
この用法の「to」は、感動的・印象的な場面の描写でよく使われる表現です。
日本語では「〜とともに」「〜を背景にして」と訳されることが多く、出来事が何かと「同時に進行している」様子を表現するのに非常に適しています。
文学的な文体を目指す英作文や、スピーチ・ニュース記事・ナレーションなどで登場頻度が高く、英語表現に奥行きと雰囲気を加えるのに最適な使い方です。
使い方18:動作の目的「〜に向けて与える意図」の「to」
この用法の「to」は、人が「ある目的・意図」で動作を行うときに、動詞とともに使われる「方向性+目的」の前置詞です。
特に、**「何かを与える・助ける・提供する・届ける」といった動作動詞の後に現れ、
「誰に向けて行動しているのか」「何のための動作か」という行為の受け手(目的語)**を明示します。
この表現は非常に日常的で、会話でも文章でも頻繁に登場します。
例文と解説
People rushed to her rescue and picked her up.
人々は彼女を助けようと駆け寄り、彼女を抱き上げた。
- 「rushed to her rescue」は「彼女を助けようと駆けつけた」。
- 「to」は「〜のために」「〜に向かって」の両方の意味合いを持ちます。
- この場合、「rescue(救助)」という名詞に向かって急ぐ=助ける意図での行動。
I came to your defense during the meeting.
会議中、私は君を擁護するために動いた。
- 「to your defense」は「君を守るために」。
- 「defense(擁護)」に向かって行動している、つまり「守る意図」の動作。
They ran to his aid when he collapsed.
彼が倒れたとき、彼らは助けに走った。
- 「to his aid」で「彼を助けるために」。
- 「aid(援助)」に向かって走る=助けたいという目的。
補足:この「to」はどんな言葉とよく組み合わさる?
この用法の「to」は、目的を表す抽象名詞とよく組み合わされます:
- to the rescue(救助のために)
- to someone’s aid(〜を助けるために)
- to someone’s defense(〜を守るために)
- to support(支援のために)
- to the service of(〜に仕えるために)
- to help(助けるために)
- to save(救うために)
これらはすべて、「何のために動いたのか」という目的が文中で明確になり、文章に行動の意味と方向性を与える働きをしています。
使い方18 まとめ
この「to」は、行動の方向だけでなく「意図・目的」を含んだ意味で使われます。
特に「to someone’s rescue」「to his aid」のような慣用表現では、「誰かを助けるために行動する」というニュアンスが、前置詞「to」によって自然に表現されています。
日常英会話からニュース記事、物語まで広く使える便利な構文であり、英語学習者にとっても非常に応用しやすい用法です。
この記事を書いた人

- イギリス人で英語と日本語のバイリンガルです!言語が大好きなので、毎日日本語を勉強しています。日本人があまり知らないネイティブ表現を紹介できれば嬉しいです。
最新の投稿
 イギリス英語2025年5月14日come up withの意味と使い方を例文で紹介
イギリス英語2025年5月14日come up withの意味と使い方を例文で紹介 ネイティブ表現2025年5月13日ネイティブの英文で英語表現を覚えよう! 050 I’m tired of all those success stories. Here is my Real Startup Story!! #2
ネイティブ表現2025年5月13日ネイティブの英文で英語表現を覚えよう! 050 I’m tired of all those success stories. Here is my Real Startup Story!! #2 ネイティブ表現2025年5月13日ネイティブの英文で英語表現を覚えよう! 050 I’m tired of all those success stories. Here is my Real Startup Story!!
ネイティブ表現2025年5月13日ネイティブの英文で英語表現を覚えよう! 050 I’m tired of all those success stories. Here is my Real Startup Story!! ネイティブ表現2025年5月13日ネイティブの英文で英語表現を覚えよう! 048 Cash buyers – turns out doesn’t have cash until summer now
ネイティブ表現2025年5月13日ネイティブの英文で英語表現を覚えよう! 048 Cash buyers – turns out doesn’t have cash until summer now